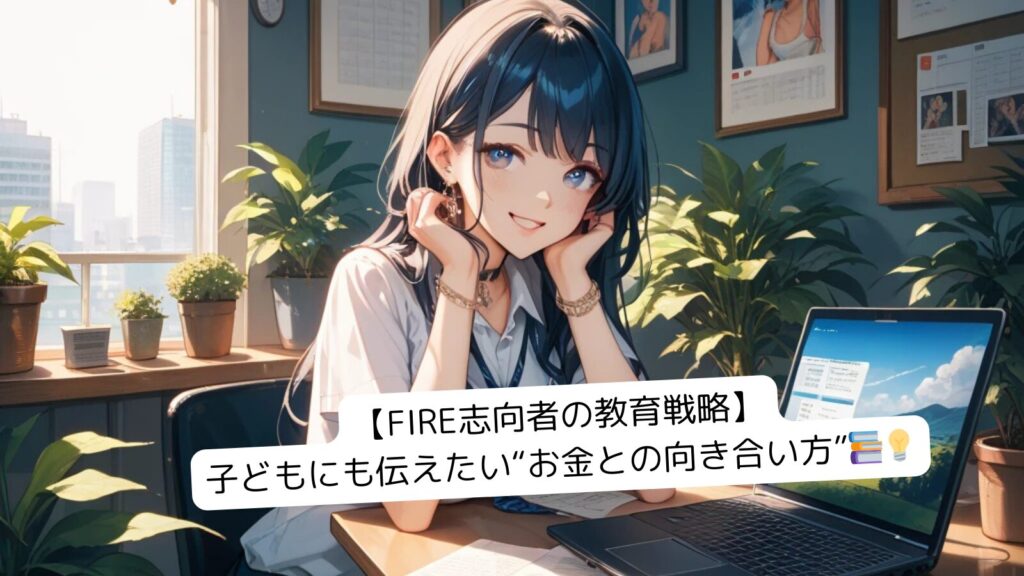
子どもにも伝えたいお金との向き合い方
FIRE(経済的自立&早期リタイア)を目指す大人が増える中で、 もう一つ注目されているのが── **“お金の教育”**です。
「親世代がお金で苦労したからこそ、子どもには自由な未来を選ばせたい」 「FIREの考え方を、次世代にも受け継ぎたい」
そう考える人が、家庭内の教育方針として“金融リテラシー”を強化し始めています。 今回は、統計データとFIRE実践者の声をもとに、 子どもにも伝えたい“お金との向き合い方”7選📚💡を紹介します!
✅ 1. 「お金=汚い」から「お金=道具」へ
📌 金融広報中央委員会「金融リテラシー調査2022」では:
- 「お金の話を子どもにするのははばかられる」と回答した親:42.8%
➡ 日本には未だ根強い「お金の話はタブー」という文化。
🧠 FIRE志向者はこれを否定し、 「お金は人生を設計するためのツール」として家庭で日常的に話題にしています。
✅ 2. “モノ”ではなく“体験”にお金を使う習慣
📌 子どもの幸福度に関する国際調査(UNICEF 2021):
- 体験型の支出が子どもの幸福度に強く影響していると判明
🧠 FIRE実践者は、「ご褒美=モノ」ではなく「時間・思い出・旅行」に投資。 金銭感覚だけでなく、価値観教育にもなっています。
✅ 3. 「投資=危険」ではなく「長期投資=学び」として教える
📌 金融庁「つみたてNISA利用者アンケート(2023年)」
- 初めて投資した年齢が“20代未満”の割合:7.6%
- そのほとんどが「親や教師の影響で投資に興味を持った」と回答
🧠 FIRE家庭では、ジュニアNISAや投資信託の話を子どもと共有し、 ゲーム感覚で“複利”や“価格変動”を学ぶ環境を作っています。
✅ 4. 「おこづかい=訓練の場」とする
📌 FP協会の調査(2022年)
- 「おこづかいを定額で渡す」家庭:65%
- 「お金の使い方の指導もしている」家庭:34%
🧠 FIRE家庭では、おこづかいは「使う・貯める・投資する」をセットにして教える場に。 実際に、ミニ財布・3つの封筒方式などで管理させる例も。
✅ 5. 家計の仕組みを“オープンに”見せる
📌 総務省「家計調査」+子ども経済教育の研究論文(慶應義塾大学)より:
- 「家計を共有された子どもは、金銭感覚が安定しやすい」との相関あり
🧠 FIRE志向者は、家計簿アプリ・表計算を一緒に見る機会を設けて、 「どこにいくら使って、いくら貯めているのか」を親子で話し合う文化をつくっています。
✅ 6. 「貯めるだけでなく“使い道”を一緒に考える」
📌 FP協会調査:
- 子どもが「お金を何のために貯めているのか分かっていない」割合:約40%
🧠 FIRE家庭では「将来の夢」や「欲しいモノ」だけでなく、 「誰かに喜ばれるお金の使い方は?」という視点を持たせる教育が特徴です。
✅ 7. 「働く=苦痛」ではなく「価値を届ける手段」と教える
📌 ベネッセ教育総合研究所「進路と仕事観調査2023」より:
- 小中学生の約52%が「働くことは大変そう」と回答
🧠 FIRE達成者は“労働は苦役”という価値観を払拭。 「好きなことでも収入を得られる」「仕組みで働く方法もある」など、 職業観の多様性を伝えています。
🎯 まとめ:「FIREは“個人の戦略”であり、“次世代教育”でもある」
✅ 子どもにも「自由に生きる力=金融リテラシー」を伝えることがFIRE志向者の新しいミッション ✅ 「見せて、話して、一緒に考える」ことが最大の教育 ✅ お金を知ることは、人生を選ぶ力を育てること──
▶ 情報ソース一覧:
- 金融広報中央委員会「金融リテラシー調査2022」
- 総務省「家計調査2023」
- 金融庁「つみたてNISAアンケート2023」
- FP協会「生活設計と教育」調査2022
- UNICEF「Child Well-being Report 2021」
- 慶應義塾大学経済教育研究
- ベネッセ教育研究所「進路と仕事観調査2023」
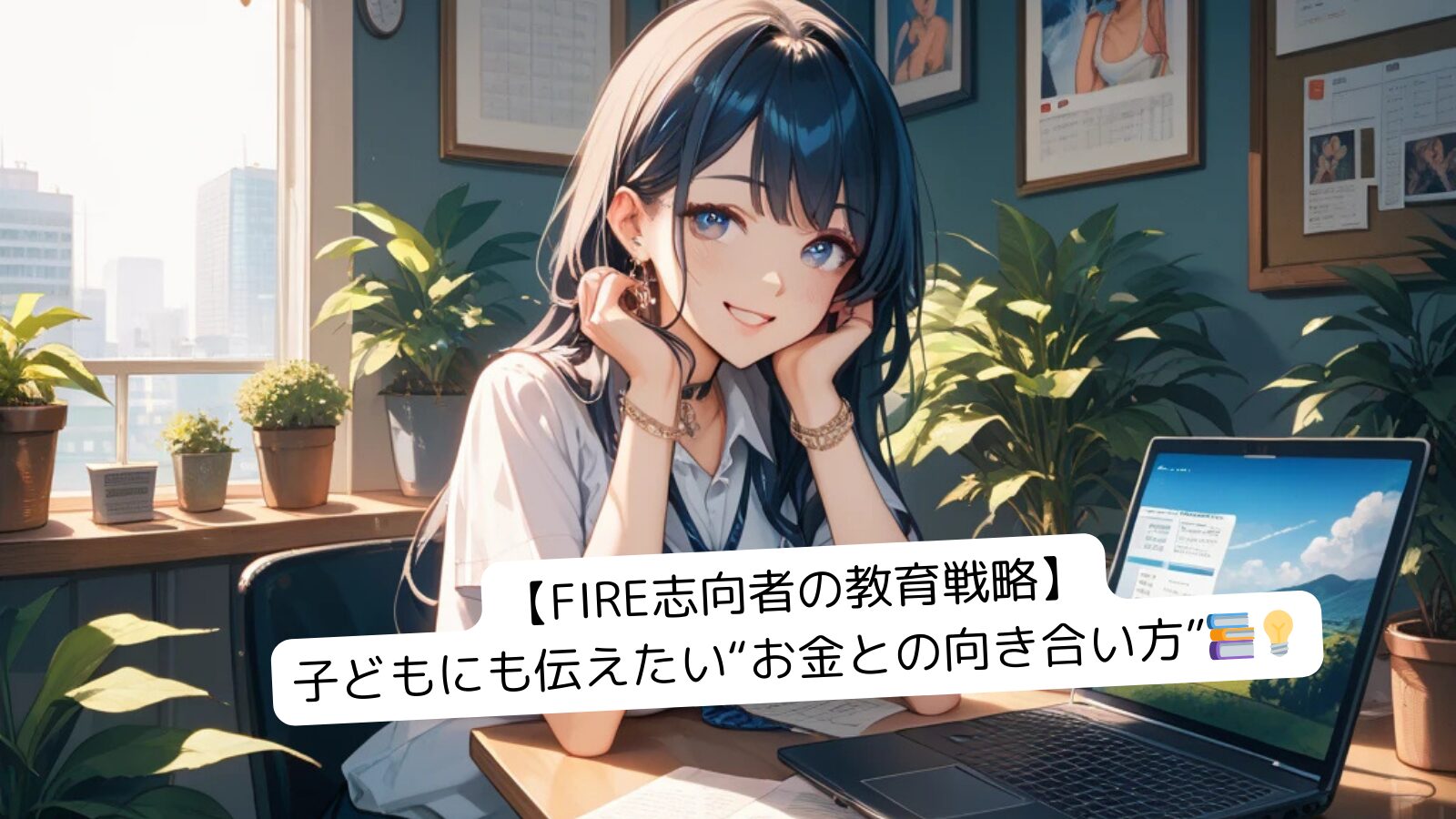



コメント